賃金とは、労働に対する対価だと思われがちです。

実際、労働基準法でも、
第11条で「この法律で賃金とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
と、賃金が労働の対価であると定義しています。
労働基準法でいう「労働の対価」とは、必ずしも、
成果や貢献度に対応して支払われるものとは限りません。
会社との契約などで支給に関する条項が明確に定められていて、
労働者が貰う権利があるものはすべて労働の対価として、
賃金となります。
つまり、労働契約に基づき、支給条件の明確なものはすべて、
労働の対象としての賃金となります。
お金は労働に対する対価?
法律上はこのようになりますが、
現実に照らしてみるとどのようなことが、
見えてくるでしょうか。
労働者は、たとえば朝の九時から夕方の六時まで働いて、
本来は、会社に対して利益を生み出したこと
又は利益に間接的につながる成果を出して、対価を得るのであって、
会社に対して、労働を渡しているわけではありません。
会社は、労働者から渡された労働を通じて、すなわち労働者を働かせて、
生産活動やサービスを行い利益を出しているのです。
本質は、このとおりなのですが、時給や時間賃金という言葉からして、
日本では、利益をどれだけ生み出したかよりも、
どれだけの多くの時間、長時間働いたかに価値を見出しがちです。
少しの時間働いて、高収入を得ようものなら、
詐欺でもしたかのような目で見られます。
では、出来高賃金や歩合制であれば、本質に近いかといえば、そうでもありません。
出来高払い賃金は、能力給、成果主義の賃金と言えますが、
その判断基準には曖昧な部分もあり、
ある企業では、それぞれが担当した部門の規模(売上規模)によって、
同じ努力、成果を出したとしても、
賃金に差がついてしまうという問題が起こったりしています。
同じようなことが、能力に差が無いのに、
たまたまその人が勤める会社の規模が違うために、
賃金に差がでてくるというのは皆さんが感じていることだと思います。
収入を増やすような成果をあげれば必ず賃金が増える、
必ずしもそのとおりではなく、
日本の成果主義は、労働者の全体の総人件費を変えず、
単なるその中での分配のための相対評価制に過ぎません。
お金は誰かに価値を与えた対価
会社に勤める以上、どこまでいっても、賃金は労働に対する対価となるのでしょうか。
私は、お金を貰うのは、誰かに与えた「価値」の対価と思います。
誰かに、喜び・満足・幸福を与えた。
誰かに、便利を与えた。
その結果、収入を得るということです。
農業、水産業、製造業、サービス業、金融業、外食産業など、
このような業全て、お客様に何らかの価値を与えていますよね。
ネットビジネスなどで起業、不動産やマネー投資のビジネスなどは、
効率よく、多くの価値を誰かに提供できるようになります。
多くの価値を与えているので、会社勤めの労働者より多くの収入を得るのもわかりますよね。
会社勤めで労働時間を会社に与えて収入を得る道を選ぶか、
私のようにネットビジネスなどで多くの価値を誰かに与えて収入を得る道を選ぶか、
どちらを選ぶのもその人の自由です。
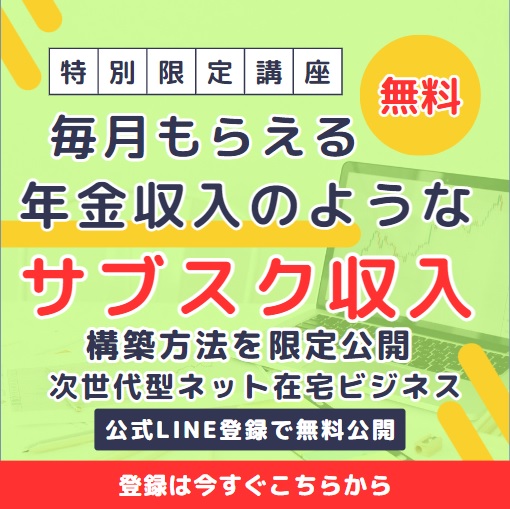

コメント